ひらめく。漢字では閃くである。音読で「せん」であり閃光などがある。
私は最近、ひらめくという言葉を文章の中で使うことになった。そして、これに類似したことばも、考えてみた。
たとえば、アイデアが浮かぶ、思いつく、直観、第六感、インスピレーション、そして気づくなどがある。類似語がこれほど多いものかと驚いた。
これらすべては共通とは言えないが、物事が瞬間的に頭に思いつくという意味があると思う。ところで、私はより日本語的な、固有の言葉がどれなのかを探ってみた。
現代語のひらめく
そうするとやはり「ひらめく」がもっとも固有日本語になりうると考えた。
そこでまず現代語の「ひらめく」を辞書で引いてみると、
1.瞬間的に光る。稲妻が光るのように使う。
2.旗、紙などがひりひらとする。また、火などがめらめらと燃え上がる。旗がひらめくなど。
3.思いつく。瞬間的に頭に浮かぶ。アイデアがひらめく
「めく」は体現・副詞についてそうみえる、そういう感じがするはっきりするという表現。ときめく、いろめくなどもある。
「ひら」は「ひらひら」という擬態語があるが、これが語源のようだ。ひらひらと木の葉が舞い落ちるなどと使われる。つまり薄いものがひるがえっている様子を表してる。
古語としてのひらめく
古語になると、「ひらめく」が「ひろめく」と同じとなり、か行四段活用で、「か、き、く、く、け、け」と活用する。意味としては、
1 あちこち動き回る。ゐも定まらずひろめきて(枕草子)([訳]居住まいもきちんとしないであちこち動き回って)
2.のたうちまわる。蛇(くちはな)出でてびりびりとひろめきて([訳]:蛇はネズミの穴から出て、ぶるぶる体を震わせのたうち回って)
やはり、現代語と同じように、一定のところに落ち着かず、’動いている’様子がうかがえる。
神霊の依り代
「ひらめく」が「ひらひら」と翻るという意味から考えると、
もともとは、「ひらひら」という動きの中に、旗や紙などが揺れるという意味があったのではないかと思われた。
旗は幡や幟(のぼり)でもあり、神霊(みたまのふゆ)を招き寄せるために掲げる意味があった。つまり神霊の依り代といういう役割があったと思われる。
よって「ひらめく」という現象は、やはり本来は巫女の神霊を呼び起こすというところから、インスピレーションという観点で、古来から使われていた日本の固有語、大和言葉ではなかったかと思われる。
ひらめいたという現象を古代では、神霊が宿るということとしてとらえていたのかもしれない。
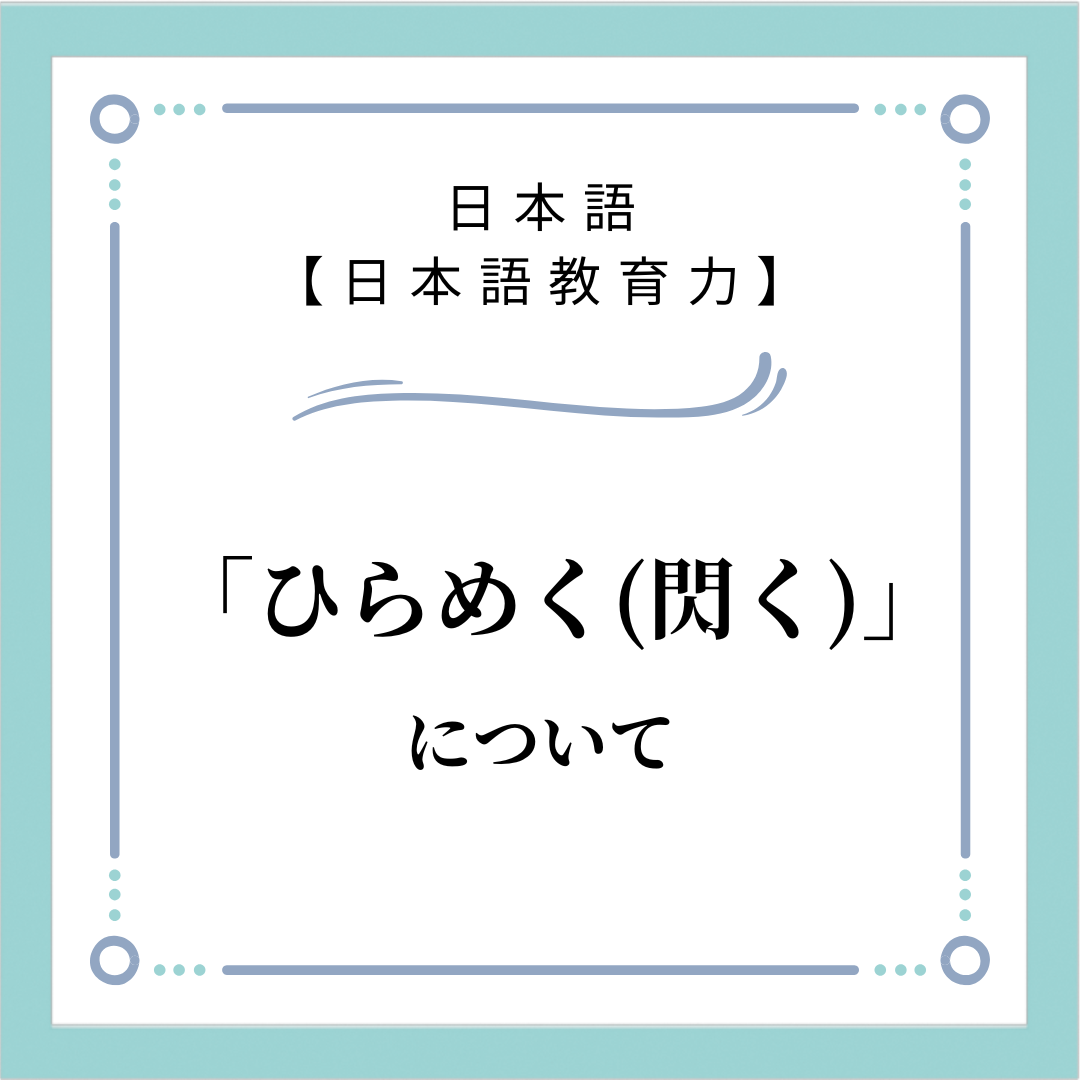
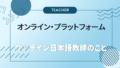
コメント