学生にとって理解しずらいもののうちに、「ても」と「のに」がある。
日本語話者にとってはこれを説明するのは
ある程度頭に知識が入っていなければならない。
ではまず、
一言で違いを述べると、
「のに」は非難、がっかりや、びっくりといった結果が意外となったときの「感情」が入ること。といえる。これを言えるだけでも、学習者の理解度は高まる。
では、より具体的な状況を示すことはできないだろうか。
さて「ても」はどんなときに使われるのだろうか。
「ても」からまず見てみよう。
「ても(でも)」の使い方
「ても」は
最近 食べても なかなか 太りません。
などがいいれいかもしれない。運動しても やせません。などもあるだろう。
これを簡単に図式すると。
A ても B
という形で、一般に教育上では、Aは前件、Bを後件といわれる。
前件とうものがあっても、後件だということだ。
もっと具体的に解釈してみると、
前件Aのことをしたが、予想していなかった後件Bが起こる。という文章となる。
さきの例文では食べたら、太るはずだったのだが、太ることはない。といった事実をのべる。
私の経験でよくあることだ。私は食べても太らないタイプだからだ。
さて、難しい用語であるが、
これを仮定的逆説といわれ、
前件に関しては、事柄が成立するかどうかわからない状況(仮定)を説明する。
さらに例をあげると
時間があっても、行きません。
明日は雨が降っても、試合をします。
のように、時間があるかどうか、雨が降るかどうかは、成立するかどうかわからない状況となる。
では「のに」はどうだろうか。
「のに」の使い方
「のに」も同じように
A のに B
と前件と後件の関係からひも解く。
英語の勉強を毎日勉強しているのに、成績が伸びない。
この場合は
前件が成立している、あるいは成立することがわかっている、こととなる。
つまり確実にある事柄が成立しているのだ。しかし
その後は期待外れのことが来ている。”成績が伸びない、不合格だった”などがくる。
「ても」と「のに」の違いはここで、
前件が成立するかどうかで、「ても」と「のに」は使い方に差があることがわかる。
さらに、
「のに」はこのような性質から
事実的逆説といわれて、先の仮定的逆説とは区別される。
苦労して、お金をかせいだのに 使いはたいしてしまった。
お金を稼いだのはここでは事実である。
事実といわれるほどに、
「のに」は
待ったのに、だれも来なかった。
という文章からわかるが、
期待とは全く異なる結果が生じる。待ったのに、だれもこないという、落胆の思いがある。
他には、がっかり、びっくり、非難といった感情が発生している。
この「感情」がキーポイントとなるであろう。もしかしたら、日本語には
感情的な表現と感情が入らない表現を分けてつけっているかもしれない。
「のに」をここで他の例文で考えてみると、
例えば
毎日カラオケで練習しているのに、歌が上手になりません。
かなり待たされた人が待たせた相手に向かって
20分も待ったのに、と非難するという使い方がよく使われるであろう。
文章だけでなく、談話全体のことや、背景などを説明することで、理解が深まると思われる。
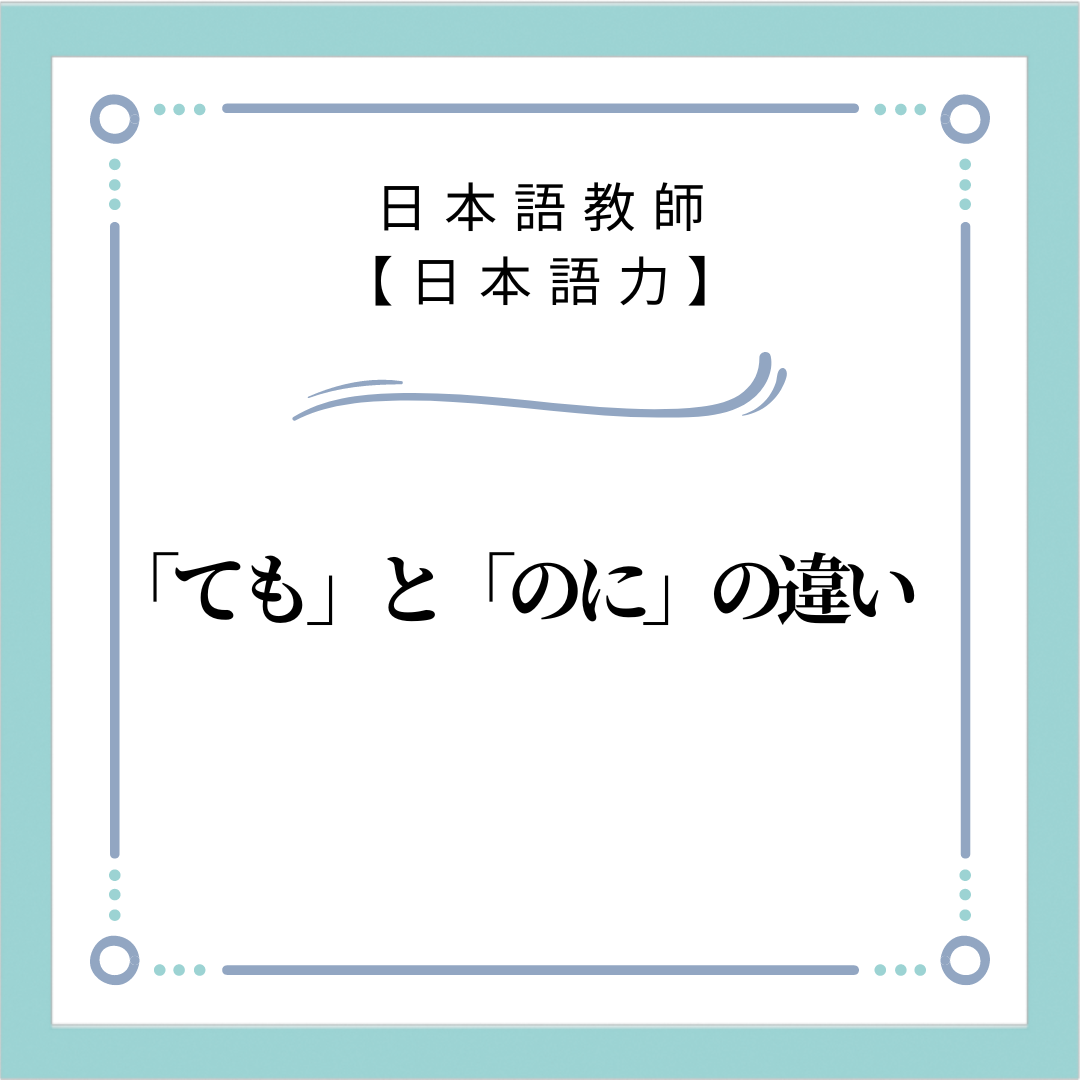


コメント