作り物
にせもの
まがいもの
これら三つの言葉は、モノや人などが本物ではないものを示している。
微妙に異なっているようではあるが、どう説明したらいいのか。
普段ネイティブ日本人が何気なく使っている言葉。
これをいかに非ネイティブ話者に伝えられることができるか。
一緒に考えてみよう。
まずは作り物から見てみよう。
つくりもの(作り物)
作り物は、読んで字のごとくで、作ったもの。
要するに、実物そっくりに作ったものと説明できる。一言で人造物あるいは模造品。
例としては
頭につけるカツラ、ドキュメンタリー番組などの作り物。事件現場の写真が作り物。
さらに、UFOの写真などを話せばけっこう伝わるかも。
英語では
Artificial product. が適当だ。
人の手で作ったことが強調されているともいえる。
もちろんまがいものともいえそうだが、人の手で作ったことが強調されていることがポイント!
また、ものだけでなく、虚構などの作品。つまり文学作品も「つくりもの」に入る。
そして人形や飾り物も「つくりもの」と言われている。けっこう範囲が広いですね。
にせもの(偽物)
にせもの、偽物は本物ではないものを表し、対象が生物以外のものに限られる。
よって、人間の場合は「偽者」となる。たとえば、敵を欺くための身代わりのものが「偽者」。
偽物の例
偽金(にせがね)、偽物の絵、偽書

英語では
Fake(形容詞). Imitation. shame, Forgery etc.
Bootleg, Knockoffという言葉もある。
偽物を「ぎぶつ」とも読む。さらに、
えせ、まがい、もどき、まやかす、などという言葉もある。
こんないっぱいあるのは
学習者には苦しいところだが、教師にも手ごわい言葉である。
日本語って微妙に異なる表現がけっこうある。
まがいもの(紛い物)
紛い物は「もの」にしか使えない。
たしかにそうだ。
そして語源は
紛らわしいから来ているようだ。
紛らわしく、たくさんのものがある、ということから
まぎらわしいもの、まがいもの、となった。
まがいものはよりぞんざいな言葉で表すときによく使われる。
よって、偽物と紛い物はほぼ同じ。
まとめ
つくりもの(つくりもの)は読んで字のごとく、作られたもの。
けっこう広範囲に使われていて、その中に、偽物という意味も含まれる。
と教える。
偽物はまがい物とほぼ同じだが、
偽物は人に仕えるが
紛い物は、モノだけ
ということで、教えることを整理してみた。
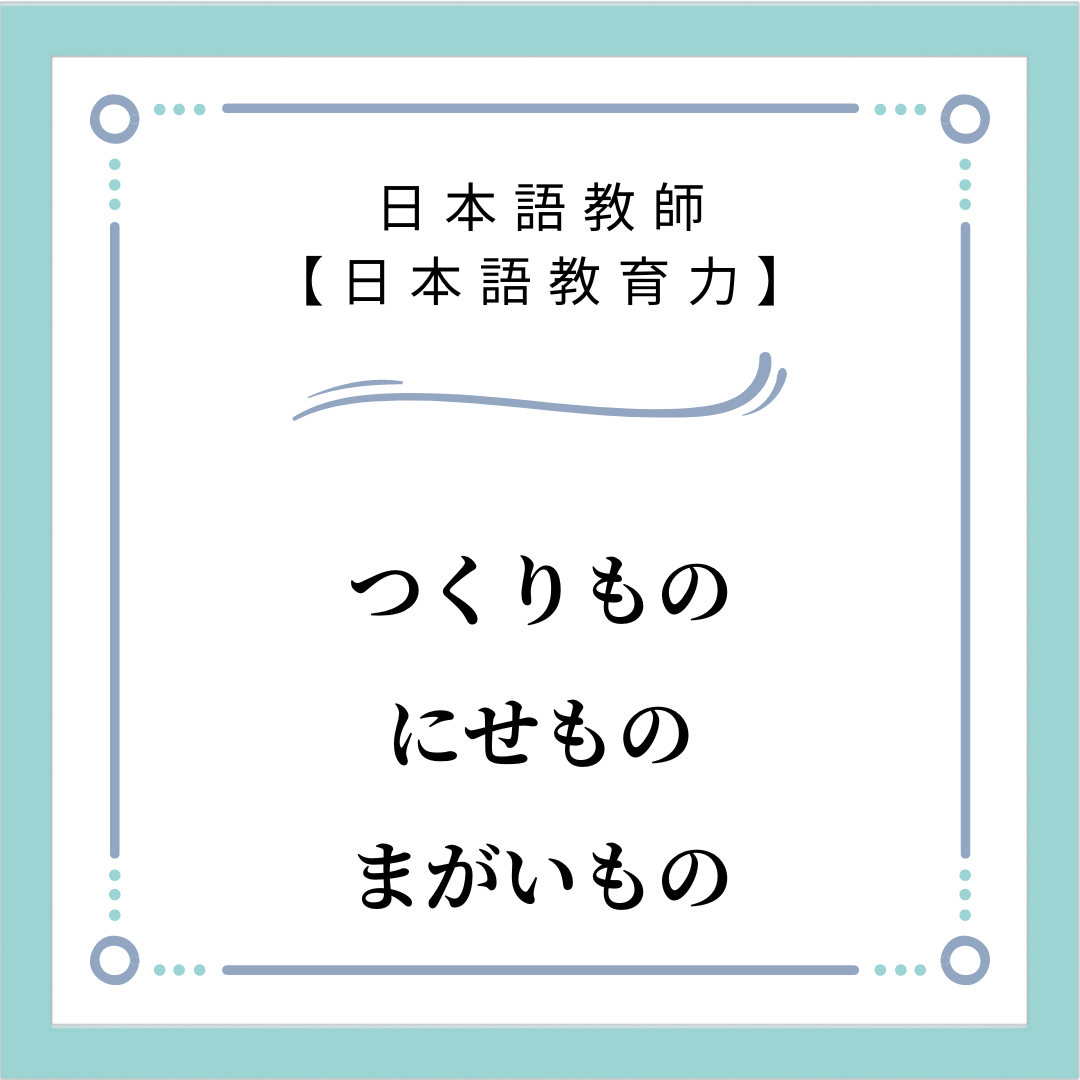

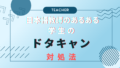
コメント