日本語教師をしていると日本人でも疑問に思わないことでも
どんどん質問してくる。
そして、日本語教師自身がそれを調べるうちに、日本語の歴史や日本語学を学ぶこととなる。
体と身体そして身とはどう違うのか。
こんな質問を受けることが多々あるだろう。
「身」を使うとどこか精神的なことも含んでいることはわかる。
では「体」とは何か。からだである。
語源も探ってみたいものだ。
「体」と「身」との違い
まず「体」は、手足や胴体を含めた体全体のこと指す。
そして、
「体」という生の肉体のことを言う。
では
「身」とは何か。これも身体と書いてからだと読むことがある。
「身」は体と比べて、精神や心も含めていうのである。
そこから慣用句や地位や立場といったより精神的なものが含まれている内容をさすこととなる。
たとえば
身が引き締まる
といった場合は、体という肉体だけでなく、精神も引き締まるというところから「身」を
使用することとなる。
身を使った慣用句など。
さきにあげた、
身が引き締まる。
それから
相手の身になって考える。
これも、相手の精神的なところを含め、特に人格を尊重するという点にフォーカスがあてられている。
身につく
これは、学習やスキルなどを学習するということである。
身に染みる
非常にとか、実感するという意味である。
他に
身の程をわきまえる。
相手の身になる。
身から出た錆。
などけっこう多いことに気づく。
学生はこんな言葉に接するたびに、困惑したり、頭を悩ますのであろう。
日本語学習者の苦労を知ることは大切だと思った。
そんなとき、教師の役割は大きいことを実感する。
おからだを大切には⇒ お身体の漢字を使うそうだ。
これも生徒には紛らわしく映るであろう。
殻と亡骸
ところで、テーマの「体(からだ)であるが、さきほど
肉体ということを指すと話した。
この語源は
から つまり殻、空、という意味から来ている。
どうしてか。体は亡骸つまり、魂(たましい)が入っていない状態だからだという。
よって、身と使いわけたのではないか。
身は魂が入っていることをいう。
これを「亡骸」などと表現する。
平安時代に始まったというこの語源。
「魂」という基準でものごとを判断していることがおもしろい。
これも、学習者に一言話してあげると、興味をしめしてくれるだろう。
言葉だけでなく、文化や背景も取り入れる教授法は、教えぐ側も力は入ると思う。
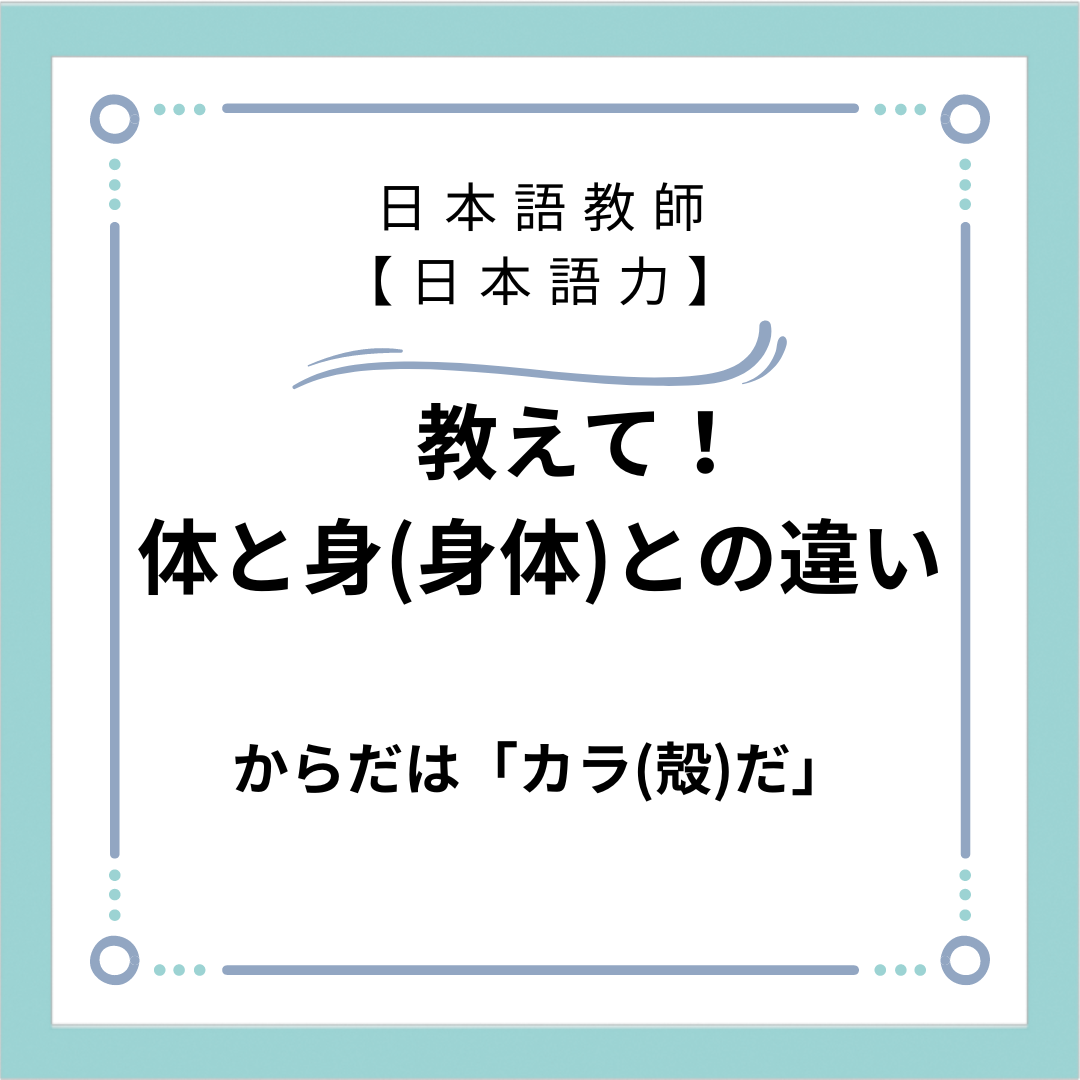


コメント